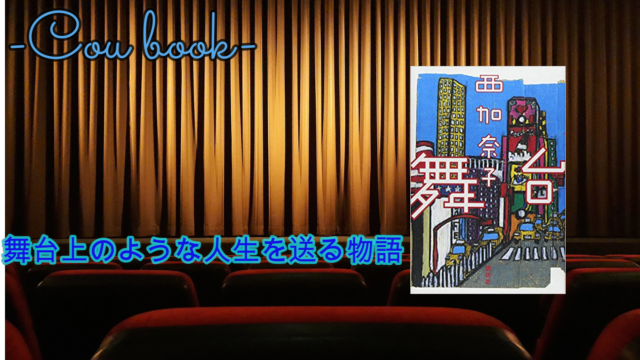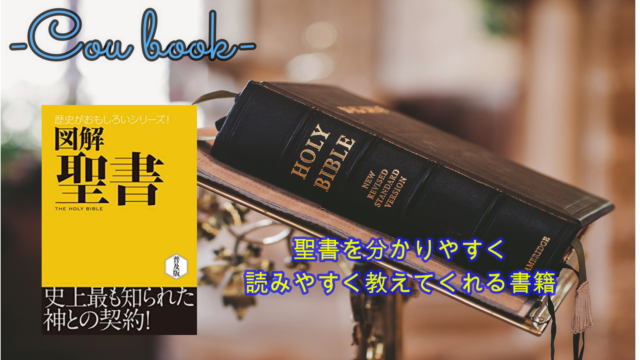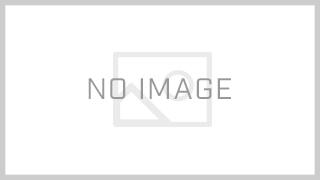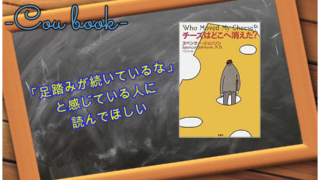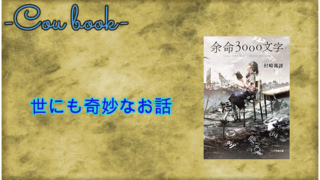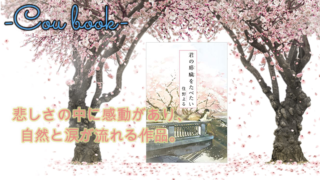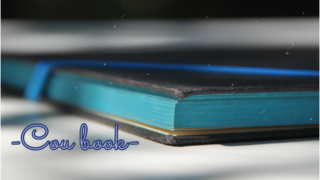正欲
Twitter上で多くの読書垢の方々が、読了ツイートとしてこの作品を上げていた。それもあり、とても気になっていた作品だ。
朝井リョウさんの作品を読むのも初めてであった為、ワクワクしながら本屋さんにて購入した作品だ。
〜こんな人におすすめ〜
おすすめ度
- 自分は理解され難い性質を持っているという人
- ハラハラした作品を読みたい方
〜作品の概要〜
○著者:朝井リョウ
○出版社:新潮社
○発売日:2021年3月26日
○ページ数:310ページ
〜著者について〜
朝井リョウ
2009年、『桐島、部活やめるってよ』で第22回小説すばる新人賞を受賞しデビュー、2012年には同作が映画化された。同年、『もういちど生まれる』で第147回直木三十五賞候補。2013年、『何者』で第148回直木三十五賞受賞。直木賞史上初の平成生まれの受賞者であり、男性受賞者としては最年少となる
。直木賞受賞後第一作『世界地図の下書き』で、第29回坪田譲治文学賞受賞。2016年、英語圏最大の文芸誌「Granta」日本語版でGranta Best of Young Japanese Novelistsに選出される。2021年、ラジオで脂質異常症であることを告白。
「桐島、部活やめるってよ」の作者であることを、調べるまで気づいていなかった。「桐島部活やめるってよ」は映像化されたものを見た事がある。その時はあまり内容も深く考えることなくなんとなく見ていた記憶がある。
〜大まかな概要〜
この物語は大きく分けて3つの場面に転換されながら話は進んでいく。1人は検事をしており家族との物語が主な男性。2人目は寝具店で働いており同級生と出会い、同じ悩みを共有する仲となって進む物語。そして最後は男性への恐怖心を抱き、そのような悩みを共有したいと「繋がり」を作ろうとする女子大生。
主にこの3人の物語が入れ替わり立ち替わり綴られおり、そして、その中で語られるのは「正欲」。このタイトルには色々な意味があるように思える。
この物語はひとつひとつが別の世界線の話というわけではなく、巡り合わせがある物語である。
〜感想〜
この作品のここがすごい!
- ハラハラ・ドキドキする物語展開。
この作品を読んでいて最も私の心情に合う言葉は「落ち着かない」だろう。このドキドキやソワソワという表現、今回に限っては「心配」に近い感情が主であったように思える。
話の内容が「性欲」というセンシティブな部分も大きく関わっていると思う。ひとつ勘違いしてほしくないのは、この作品は読む人の性欲を掻き立てるような作品では無い。もちろんそのような人もいるだろうが、私はそうではない作品であると思っている。この取り上げられている部分は「性欲」に対する違いという部分の悩みが大半だからだ。
そして私は深く考えさせられた。
考えさせられた事
この作品については2つ考えさせられた事があった。
- 性欲の多様性について述べられたこの作品はそのままの意味で受け取るべきなのか、それとも社会の大きな問題として捉えるべきなのかという点
- この作品の終わり方について
上記2つをすごく考えさせられた。
この物語にでてくる「性欲」の多様性は確かに私には理解が及ばなかった。そんな人がいるとは思えなかったからだ。
そしてこの作品のタイトルは「性欲」ではなく「正欲」である。ここで私は色んな思考をすることとなった。
「正欲」というタイトルはこの物語を読んだ上で考えると、「正しい欲」という事を表しているのでは無いかと私は思った。
そして世間的に正しいと思われる事というのは、総じて多数派の意見に収束しがちである。その為、「正しい欲」へと多数派の人々は違うものにたいして、「欲を正そう」とする。それは多様性を認める事とは結果的になっていない。そんな物語の内容になっているように私には思えている。
ここでは私にとって特殊に思える「性癖」が出てくる。このような人が現実に存在しているのであれば興味という面でとても話を聞いてみたい。しかし、もちろん本人にとってセンシティブな部分である為、人に共有したく無いという気持ちが生まれるのも当然なことであろう。この興味というの失礼な事なのか、それとも知ってほしい事なのか、人によって違う為難しい内容である。
しかし、私は理解したいという理解する立場に私がいるというものではなく、本当に自分との違いに興味がある。しかし、その興味を向けられる側としての立場を考えると、知ってほしいという人以外には嫌悪する対象ではあるのだと思う。
そのような理解も深まったように感じる。
そしてこの作品の終わり方だ。
この作品を読み終えた時、この終わり方にしたのはどのような意図があるのだろうと思った。私はこの作品を読み終える前に、先に書いたことを考えていた。それを踏まえた上でこの作品は今現在、作者が伝えたい事を皆に考えてほしいという想いがあるのではないかと私は思った。
生き方の多様性があるという事が、多くの人に存在を認知されてきているこの時代だからこそ、この作品の問題は今もなお続く問題だからこそこの作品の終わり方なのだと思った。
今のような時代だからこそ、この作品は読んでほしい作品だ。
〜最後に〜
初めに書かれた文章に私は心を奪われた。
どうして人間は生きているのか、生きる意味とは何なのか等という疑問を呈したとて、
去年の夏は暑かったとでも言うように、
「自分にもそういう時期があったけれど」なんて語ってきたりします。
クソみたいな返答です。
この文章に私は同感し、この作品に心を奪われていったのだ。
また終始ハラハラ・ドキドキする展開であった。
皆の心が不安定になってゆくのが分かり、どうしても落ち着かなかったのだ。内容も読むのが苦しいという内容というわけではなく、何か心に訴えかけられ考えさせられる作品であった。
この作品を今読めてよかったと思えた。
読んでない方は是非一度読んでみてください。